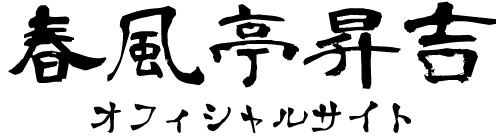水前寺成趣園能楽殿
喜秀会 秋季大会
令和3年10月31日(日)
水前寺成趣園能楽殿
高砂
醍醐天皇の御世の延喜年間のこと、九州阿蘇神社の神主友成は、都見物の途中、従者を連れて播磨国の名所高砂の浦に立ち寄ります。友成が里人を待っているところに、清らかな佇まいをした、一組の老夫婦。松の木陰を掃き清める老夫婦に友成は、高砂の松について。二人は友成に、「この松こそ高砂の松であり、遠い住吉の地にある住の江の松と合わせて「相生(あいおい)の松」と呼ばれている」謂われを教えます。そして『万葉集』の昔のように今の延喜帝の治世に和歌の道が栄えていることを、それぞれ高砂、住の江の松にたとえて、賞賛。老翁はさらに、和歌が栄えるのは、草木をはじめ万物に歌心がこもるからだと説き、樹齢千年を保つ常緑の松は特にめでたいものであるとして、松の由緒語り。やがて老夫婦は、「自分たちは高砂と住吉の「相生の松」の化身である」と告げると、住吉での再会を約して夕波に寄せる岸辺で小船に乗り、そのまま風にまかせて、沖へと姿を消して行きました。残された友成の一行は、老夫婦の後を追って、月の出とともに小舟を出し、高砂の浦から一路、住吉へ向かいます。住吉の岸に着くと、男体の住吉明神が姿を現しました。月下の住吉明神は、神々しく颯爽と舞い、悪魔を払いのけ、君民の長寿を寿ぎ、平安な世を祝福するのでした。
頼政
旅の僧が京都から奈良に向かう途中、宇治の里に赴き、一人の老人に出会い。僧に宇治の名所を教えてほしいと頼まれた老人は、僧を平等院へと案内します。老人はかつて源三位頼政がこの場所に扇を敷いて自害したことを話し、自身が頼政の幽霊であると名のり、姿を消します。夜、頼政の幽霊が現れ、平家に敗れたときの様子を語ります。高倉の宮に謀反を勧めた結果、都落ちすることになり、平家に追われた頼政らは宇治川の橋板を外し、対岸で追手を待ち構えました。平家方は田原の又太郎忠綱が先陣として、宇治川に馬を乗り入れて対岸に攻め込み、合戦となります。頼政の息子二人も討たれてしまい、ついに頼政は平等院の庭の芝に扇を敷いて、辞世の和歌を詠んで自害した旨。
融
秋の名月の日。都に上った東国の僧が、六条河原院まで来たところ、ひとりの汐汲みの田子を背負った老人が現れます。六条河原で汐汲みとは、と訝る僧に、老人は、この河原院はかつて河原左大臣といわれた源融が、陸奥千賀の塩竃の景色をそのまま都に移して作って住んだところだと謂れを語るうちに、月が出てあたりを照らし、趣深い秋の夕景色がふたりの眼前に広がります。
庭の景色を眺めつつ、僧と老人がなおも言葉を交わします。融は、毎日難波から潮を汲ませて、院の庭で塩を焼かせて一生の楽しみとしたが、後を継ぐ人もなく、この河原院は荒れ果ててしまった……。そう嘆く老人を慰めようとしたのか、僧は都の山々の名所を教えてほしいと頼みます。あちこち挙げながら、一緒に仲秋の名月を愛でるうち老人は、つい長話をしたと言って水を汲む様子を見せた後、姿を消してしまいます。
近くに住む者から、河原院と融の大臣の物語を聞いた僧は、先ほどの老人が大臣の亡霊だったと思い当たり、眠りにつきます。すると在りし日の姿で融の亡霊が現れ、月光に照らされながら華麗な遊楽に乗って舞うのでした。融は、時を忘れたかのようにこの月夜に興じていましたが、夜明けとともに、名残惜しい面影を残して、再び月の都へ戻っていきました。
西王母
古代中国、周の穆王の時代のこと。宮殿で祝賀に興じているところに、一人の若い女。女は、手に桃の花が咲いた枝を持っていました。この花は、三千年に一度だけ咲くという桃で、帝王の威徳により、時機を得て今咲いたのだと女は言い、この花を帝王に捧げました。帝王は、伝え聞く西王母の庭園の桃かと女に問いますが、女は答えず「桃花物言わず、幾年か過ぎた」「三千年ごとに実るという桃が、今年は花開く春に巡り逢った」という古歌を引き、帝王の治世を讃えます。その後、女は、西王母の化身であると明かし、後で真の姿となって桃の実を捧げましょうと帝王に約束して天に去ります。
王が、管弦の催しを開いて西王母を待っていると、西王母が天女の姿で現れました。西王母は侍女に持たせていた桃の実を帝王に献上します。酒宴が始まり、人も花も酔うなかで、西王母は軽やかに舞を舞い、御代を寿ぎながら、春風に乗って、孔雀や鳳凰とともに天へ上がり、消えていきました。
桜川
日向国、桜の馬場の西に、母ひとり子ひとりの貧しい家がありました。その家の子、桜子は、母の労苦に心を痛め、みずから人商人に身売り。人商人が届けた手紙から桜子の身売りを知った母は、悲しみに心を乱し、泣きながら家を飛び出して、桜子を尋ねる旅に。
それから三年。桜子は、遠く常陸国の磯辺寺の住職に弟子入りしていました。春の花盛り、住職は桜子らとともに、近隣の花の名所、その名も桜川に花見に出かけます。折しも桜川のほとりには、長い旅を経た桜子の母がたどり着いていました。
狂女となった母は、川面に散る桜の花びらを網で掬い、狂う有様を見せていた。住職がわけを聞くと、母は別れた子、桜子に縁のある花を粗末に出来ないと語ります。そして落花に誘われるように、桜子への想いを募らせて狂乱の極み。
やがて母は住職が連れてきた子と対面。その子が桜子であるとわかり、母は正気に戻って嬉し涙を流し、親子は連れ立って帰ります。母も出家して、仏の恵みを得たことから、親子の道は本当に有難いという教訓が語られます。
海人
藤原不比等の子、房前の大臣は、亡母を追善しようと、讃岐の国志度の浦を訪れます。
志度の浦で大臣一行は、ひとりの女の海人に出会いました。一行としばし問答した後、海人は従者から海に入って海松布を刈るよう頼まれ、そこから思い出したように、かつてこの浦であった出来事を語り始めます。淡海公の妹君が唐帝の后になったことから贈られた面向不背の玉が龍宮に奪われ、それを取り返すために淡海公が身分を隠してこの浦に住んだこと、淡海公と結ばれた海人が一人の男子をもうけたこと、そして子を淡海公の世継ぎにするため、自らの命を投げ打って玉を取り返したこと……。語りつつ、玉取りの様子を真似て見せた海人は、ついに自分こそが房前の大臣の母であると名乗り、涙のうちに房前の大臣に手紙を渡し、海中に。
房前の大臣は手紙を開き、冥界で助けを求める母の願いを知り、志度寺にて十三回忌の追善供養。法華経を読誦しているうちに龍女となった母が現れ、さわやかに舞い。
敦盛
源氏の武将、熊谷次郎直実は、一の谷の合戦で年端も行かない平敦盛を討ち取ったのですが、あまりの痛ましさに無常を感じ、出家して蓮生と名乗りました。敦盛の菩提を弔うために一の谷を訪れた蓮生が回想にふけっていると、笛の音が聴こえ草刈男たちが現れます。蓮生が、話しかけると、中のひとりが笛にまつわる話をします。
蓮生が不審に思うと、男は、「自分は敦盛に縁のある者で、十念を授けて欲しい」と話します。蓮生が経をあげると、男は、敦盛の化身であることをほのめかして姿を消しました。
その晩、蓮生が敦盛の菩提を弔っていると、その霊が往時の姿で現れます。敦盛は、自分を弔う蓮生は、以前は敵でも今は真の友であると喜び、懺悔の物語。寿永二年の秋の都落ち、須磨の浦での侘び住まい、平家一門の衰勢を語り、最期を迎える前夜の陣内での酒宴のさまを想起して舞を舞います。そして、一の谷で、舟に乗ろうと波打際まで進んだところで、熊谷次郎直実に呼び止められて一騎打ちとなり、討たれた戦いの場面を見せ、今では敵ではなく、法の友である蓮生に回向を頼んで去っていきます。
求塚
早春のある日。僧の一行が生田の里に到ると、菜摘みの女たちが現れる。女たちは僧を土地の名所へと案内するが、僧が“求塚”の名を出すや、女たちは一斉に口をつぐみ、菜摘みに興じつつ帰っていってしまう。ところが、その中の一人だけはその場に残ると、僧を求塚へ案内する。この塚は、想いを寄せる二人の男の間で板挟みとなり入水自殺した、菟名日処女の墓であった。女は処女の故事を身の上のように語ると、救済を願いつつ姿を消してしまう。
僧が弔っていると、地獄の苦患に憔悴した姿の処女の亡霊が現れた。仏法の力によって視界を覆う業火の煙を晴らした処女だったが、そこに現れたのは、二人の男と、その争いに巻き込まれて死んだ鴛鴦の亡魂であった。地獄の炎で焼き尽くされ、責め苛まれる処女。彼女は果てなき闇路に迷い続ける姿を見せつつ、消えてゆくのだった
梅枝
甲斐国身延山の僧たちが、諸国を巡って修行をしています。摂津国住吉で突然の雨にあい、質素な庵に住む女に一夜の宿を借りることにしました。
僧は、庵に舞楽の太鼓や舞の衣装が置かれているのを不思議に思い、女に尋ねます。女は、住吉大社の伶人であった夫・富士と天王寺の伶人・浅間が内裏の管絃の役をめぐって争い、管絃の役は夫・富士に決まったこと、それを恨みに思った浅間に夫が殺された顛末を語ります。富士の妻は夫を恋しく思いながら形見の太鼓を打って心を慰めていましたが、ついに亡くなってしまったことを語り、僧に回向を頼んで姿を消します。
夜、僧たちが読経していると、夫の形見である舞の衣装をまとった富士の妻の亡霊が現れます。亡霊は、非業の死を遂げた夫への恋慕で涙にくれた生前を回想し、越天楽今様を謡い、懺悔の舞を舞います。そして、楽の音と松風の音が一つになって、暁の闇のなかに姿を消す。
三井寺
秋の頃、京都・清水寺にて、駿河国の清見が関から来た女が、観音様に向かい熱心に祈りを捧げていました。彼女は、わが子の千満が行方不明になったため、再び逢いたい一心で、都までお参りに来ていたのです。祈りの間にしばしまどろんだ女は、霊夢を見ます。そこに、清水寺門前の者が来て夢を占い、わが子に会いたいなら近江国の三井寺へ急いでいきなさいというお告げだと判定します。女は喜び、早速三井寺へ向かいます。
三井寺では、ちょうど八月十五日を迎え、僧たちが月見をしようと待ち構えています。そこには、三井寺の住僧に弟子入りした千満の姿もありました。人々が、中秋の名月を鑑賞しているところに、物狂いとなった千満の母が現われます。興味を持った能力(寺の下働きの男)の手引きで、女は女人禁制の寺に入り込みます。女は鐘の音を聞いて面白がり、三井寺の鐘の来歴を語り、鐘楼に上がり込んで鐘を撞き始めます。さらに女は鐘にまつわる諸々の故事を引き、古歌や古詩を詠じ、鐘と月とを縁として仏法を説きます。
女を見て何かを感じた千満は、師僧を通じて女の出身地を聞き、声をかけます。女と千満は互いに母子だと認め合い、涙の対面を果たします。そしてふたりは故郷へ連れ立って帰り、豊かに暮らします。
葛城
ある冬のこと。出羽国羽黒山の山伏の一行が、大和国葛城山へ入りました。ところが一行は山中で吹雪に見舞われ、木陰に避難します。そこに近くに住む女が通りがかります。途方に暮れていた彼らを気の毒に思い、女は一夜の宿を申し出て、一行を自分の庵に案内します。
庵で女は、「しもと」と呼ぶ薪を焚いて山伏をもてなし、古い歌を引きながら、葛城山と「標」にまつわる話。話のうちに夜も更け、山伏は夜の勤行。すると女は、自分の苦しみを取り去るお祈りをしてほしいと、言い出しました。山伏は、女の苦しみが人間のものでないことに気づき、問いただします。女は、自分は葛城の神であり、昔、修験道の開祖、役の行者の依頼を受けて、修行者のための岩橋を架けようとしたが、架けられなかった、そのため、役の行者の法力により蔦葛で縛られ、苦しんでいると明かし、消え去ります。
山伏たちが、葛城の神を慰めようと祈っていると、女体の葛城の神が、蔦葛に縛られた姿を見せました。葛城の神は、山伏たちにしっかり祈祷するよう頼み、大和舞を舞うと、夜明けの光で醜い顔があらわになる前にと、磐戸のなかへ入っていきました。
清経
平家一門が都落ちした後、都でひっそり暮らしていた平清経の妻のもとへ、九州から、家臣の淡津三郎。三郎は、清経が、豊前国柳が浦の沖合で入水したという悲報をもってやって来たのです。形見の品に、清経の遺髪を手渡された妻は、再会の約束を果たさなかった夫を恨み、悲嘆にくれます。そして、悲しみが増すからと、遺髪を宇佐八幡宮に返納してしまいます。
しかし、夫への想いは募り、せめて夢で会えたらと願う妻の夢枕に、清経の霊が鎧姿で現れました。もはや今生では逢うことができないふたり。再会を喜ぶものの、妻は再会の約束を果たさなかった夫を責め、夫は遺髪を返納してしまった妻の薄情を恨み、互いを恨んでは涙します。やがて、清経の霊は、死に至るまでの様子を語りながら見せ、はかなく、苦しみの続く現世よりは極楽往生を願おうと入水したことを示し、さらに死後の修羅道の惨状を現します。そして最後に、念仏によって救われる。
野宮
晩秋の9月7日、旅僧がひとり、嵯峨野を訪れ、伊勢斎宮の精進屋とされた野の宮の旧跡に足を踏み入れます。昔そのままの黒木の鳥居や小柴垣を眺めつつ参拝していると、榊を持った上品な里女が現れます。女は、僧に向かい、毎年必ず長月七日に野の宮にて昔を思い出し、神事を行う、ついては邪魔をしないで立ち去るようにと話します。僧が、昔を思い出すとはどういうことかと尋ねると、かつて光源氏が、野の宮に籠もっていた六条御息所を訪ねてきたのがこの日だと告げ、懐かしそうに御息所の物語を語ります。そして、自分こそが、その御息所だと明かし、姿を消してしまいました。
別に現れた里人から、改めて光源氏と六条御息所の話を聞いた僧は、御息所の供養を始めます。すると、牛車に乗った御息所の亡霊が現れます。御息所は、賀茂の祭りで、源氏の正妻葵上の一行から、車争いの屈辱を受けたことを語り、妄執に囚われている自分を救うため、回向して欲しいと僧に頼みます。野の宮での源氏との別れの記憶にひたりながら、御息所は、しっとりと舞い、過去への思いを深く残す様子で、再び車に乗り、姿を消しました。
弱法師
河内国高安に住む高安通俊は、他人の讒言を信じて、実子の俊徳丸を家から追い出しました。後悔した通俊は、俊徳丸の現世と来世の安楽を願い、春の天王寺で七日間の施行を営みます。その最終日、弱法師(よろぼし)と呼ばれる盲目の若い乞食が、施行の場に現れました。実はこの弱法師は俊徳丸その人でした。
弱法師が施行の列に加わると、梅の花びらが袖に散りかかります。花の香を愛でる弱法師を見て、通俊は花も施行の一つだと言いました。弱法師も同意し、仏法を称賛し天王寺の由来を語りました。通俊は、弱法師が我が子、俊徳丸であると気づきますが、人目をはばかり、夜に打ち明けようと考えます。通俊は弱法師に日想観を勧め、弱法師は、難波の絶景を思い浮かべますが、やがて狂乱し、あちこちにつまずき転び、盲目の悲しさに打ちのめされます。
夜更けに通俊は、弱法師すなわち俊徳丸に父であると明かします。俊徳丸は恥ずかしさのあまり逃げますが、通俊は追いついて手を取り、高安の里に連れ帰りました。
砧
九州の芦屋某が訴訟のために上京してからしばらく経ち、国元の妻は夫の帰国を待ちわびています。離れ離れになってから三年目の秋、侍女の夕霧が一人だけ帰郷してきました。妻は夫の無情を嘆きますが、せめてもの慰みにと、里人の打つ砧を取り寄せて打ち、砧の音がわが思いをのせて都の夫のもとへ通じるようにと祈る。しかし、今年も帰国できないという知らせを聞いて、妻は病となり、ついに命を落とします。
帰国した夫がそれを知って弔うと、妻の亡霊がやつれ果てた姿で現われます。妻は、恋慕の執心にかられたまま死んだために、地獄に落ちていたのですが、いまだに夫が忘れられず、恋と怨みの同居するやるせなさを夫に訴え、そのつれなさを責めますが、夫の読経の功徳で成仏します。
殺生石
玄翁という高僧が下野国那須野の原を通りかかります。ある石の周囲を飛ぶ鳥が落ちるのを見て、玄翁が不審に思っていると、ひとりの女が現れ、その石は殺生石といって近づく生き物を殺してしまうから近寄ってはいけないと教えます。玄翁の問いに、女は殺生石の由来を語ります。
「昔、鳥羽の院の時代に、玉藻の前という宮廷女官がいた。才色兼備の玉藻の前は鳥羽の院の寵愛を受けたが、狐の化け物であることを陰陽師の安倍泰成に見破られ、正体を現して那須野の原まで逃げたが、ついに討たれてしまう。その魂が残って巨石に取り憑き、殺生石となった」、そう語り終えると女は玉藻の前の亡霊であることを知らせて消えます。
玄翁は、石魂を仏道に導いてやろうと法事を執り行います。すると石が割れて、野干の精霊が姿を現します。野干の精霊は、「天竺、唐、日本をまたにかけて、世に乱れをもたらしてきたが、安倍泰成に調伏され、那須野の原に逃げてきたところを、三浦の介、上総の介の二人が指揮する狩人たちに追われ、ついに射伏せられて那須野の原の露と消えた。以来、殺生石となって人を殺して何年も過ごしてきた」と、これまでを振り返ります。そして今、有難い仏法を授けられたからには、もはや悪事はいたしませんと、固い約束を結んだ石となって、鬼神、すなわち野干の精霊は消えていきます。
高野物狂
常陸国の有力者・平松殿は、その臨終に際し、家臣の高師四郎に我が子・春満丸の養育を託していた。しかし、四郎の留守に春満丸は失踪してしまう。置き手紙を読んだ四郎は、春満を慕って放浪の旅に出るのであった。
高野山に辿り着いた四郎は、僧に咎められながらも、寂寞の霊地にやって来た法悦にひたって舞い戯れる。そうするうち、四郎は高野山に身を寄せていた春満丸と再会し、二人は下山して平松の家を再興させるのであった。
藤戸
源平の合戦に勝利した源氏方の武将、佐々木盛綱は、備前国児島にある藤戸の合戦で、馬で海を渡る快挙を成し遂げ、先陣の功を挙げました。それにより、児島を領地に賜りました。春の吉日に、盛綱は初めて領地入りしました。すると一人の老婆が現れ、我が子を殺したと名指しで、盛綱を咎めます。初めは、知らぬ存ぜぬを通していた盛綱も、再三の老婆の追及とその哀れな様子に心を動かされ、とうとう告白します。源氏が戦陣を構えた藤戸は、平家の陣地と海で隔てられ、戦況は膠着していました。盛綱は地元に住む若い漁師から、馬で渡れる浅瀬ができる場所と日時を聞き出します。このことを、平家方はもちろん、味方にも知られたくなかった盛綱は、他言を恐れて漁師を殺し、海に沈めてしまったのです。この話を聞いた老婆は、半狂乱となり、自分も殺せと転げまわり、我が子を返せと盛綱に迫ります。盛綱は老婆をなだめ、漁師を回向することを約束し、家に帰らせました。
盛綱が、藤戸の海辺で管弦講を催し、般若経を読誦して漁師を弔っていると、漁師の亡霊が海上に姿を現します。亡霊は、無惨にも殺された恨みを語り伝えに来たと言い、刺し通されて海に沈められた惨劇を見せるのでした。亡霊は、悪龍の水神と化して、恨みを晴らそうとしていたのですが、意外にも回向を賜ったことに感謝し、彼岸に至って成仏の身となりました。
西行桜
都の外れ、西山にある西行の庵は桜の美しいことで有名でした。毎年、花見の客が訪れ、にぎわうのですが、庵主の西行は、静かな隠遁生活が破られることを快く思わず、能力(従者)に花見を禁止する旨。ところが、禁止令を知ってか知らずか、都の花見客が訪れ、案内を乞うてきました。西行も無下に断れず、庭に入るのを許します。しかし静かな環境を破られてしまったという思いから、「花見んと群れつつ人の来るのみぞ、あたら桜のとがにはありける」と歌を詠みました。
その夜、西行が桜の木蔭でまどろんでいると、夢の中に老人が現れました。老人は、草木には心がないのだから、花に罪はないはずだ、と先ほどの西行の詠歌に異議を唱えてきます。西行は納得し、そういう理屈を言うのは、花の精だからであろう、と老人に語りかけました。老人は、自分は老木の桜の精であり、花は物を言わないけれど、罪のないことをはっきりさせたくて現れたのだと明かします。桜の精は、西行と知り合えたことを喜び、都の花の名所を紹介し、春の夜の一時は千金に値すると惜しみながら、舞を舞いました。
やがて時は過ぎ、春の夜が花の影から明け初めるなか、西行は夢から覚め、桜の精の姿は、散る花とともに静かに、跡形もなく消えていきました。
自然居士
若い説経師が、京都・雲居寺に人を集めて、七日間の説法を行っていました。その最終日、一人の孤児の女の子が、美しい着物を携えて現れます。女児は持参した着物を供養の品として、亡き両親を弔ってほしいと、自然居士に申し出ます。その健気な心に、居士も聴衆も涙します。
ところが、その女児は、東国から来た人商人にわが身を売って、着物を調達していました。女児は、追ってきた人商人に連れ去られてしまいます。そのことを知った自然居士は、女児を助けようと人商人一行を追いかけ、彼らが琵琶湖のほとりで舟を出そうとするところに間に合います。自然居士は舟を引き留めて乗り込み、女児を解放しないなら、自分も人商人と子どもについていくと決意を述べます。舟から下りなければ、殺してやろうかと言う人商人の脅しにも負けず、自然居士は、決して下りようとはしません。
仏法に仕える自然居士に、手を出すことのできない人商人は、しぶしぶ女児の解放を決めます。そして募る不満を晴らすため、自然居士に舞を舞わせ、辱めを与えようと考え、女児の解放の条件にしました。人商人のたくらみを知りつつも、自然居士は彼らの求めに応じて、さまざまな舞を惜しみなく見せます。そして無事に女児を解放させ、一緒に都へと帰る。
小塩
京都西郊 大原山へと花見に訪れた都人たち。そこへ一人の老人が、花盛りの山中に浮かれつつやって来た。姿こそ賤しくとも、心の花は失っていないと言う老人。彼は、一行を伴って遥かに春の洛中を眺めると、「神代のことが思い出される」と呟く。それは昔、帝の后がこの地を訪れた折、供奉していた在原業平の詠んだ歌であった。そう明かすと、老人は花々の情趣に興じつつ、そのまま姿を消してしまう。
やがて花の蔭に休らう一行のもとへ現れた、車に乗った一人の貴人。彼こそ、在原業平の霊魂であった。業平は、多くの女性と契りを交わした在りし日を偲び、中でも帝の后を慕い続けた自らの思いを吐露する。この地こそ、その想いの丈を歌に詠んだ場所。業平は、往時の記憶に浸りつつ舞を舞うと、曙の空に消えてゆくのだった。
鵺
熊野から京都をめざしていた旅の僧が、摂津国芦屋の里に着き、里人に宿泊先を求めますが断られます。僧は、里人から紹介された川沿いの御堂に泊まることにした。夜半、そこに埋もれ木のような舟が一艘漕ぎ寄せ、姿の定まらない怪しげな舟人が現れ、僧と言葉を交わします。はじめ正体を明かさなかった舟人も、「人間ではないだろう、名は?」と問いかける僧に、自分は怪物・鵺の亡霊であると明かします。そして、近衛天皇の御代に、天皇を病魔に陥らせたところ、源頼政に射抜かれ、退治された、という顛末を語り、僧に回向を頼んで夜の波間に消えていきました。
しばらくして、様子を見にきた里人は、改めて頼政の鵺退治の話を語り、退治されて淀川に流された鵺がしばらくこの地に滞留していたと僧に伝えます。話を聞いた僧が読経して鵺を弔っていると、鵺の亡霊がもとのかたちで姿を現します。鵺の亡霊は、頼政は鵺退治で名を上げ、帝より獅子王の名を持つ名剣を賜ったが、自分はうつほ舟に押し込められ、暗い水底に流されたと語ります。そして、山の端にかかる月のように我が身を照らし救い給え、と願いながら、月とともに闇へと沈んでいくのでした。