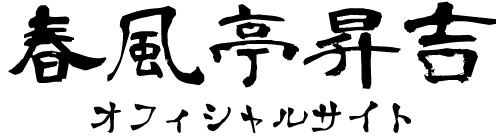『よそう、夢になるといけねえ』
師走になると、落語家は名作をやりたくなる。
年末の噺といえば、「芝浜」です。
酒癖の悪い亭主が、女房の嘘をきっかけに酒を断ち、三年かけて人生を立て直す。
そして最後、酒を口にする寸前でこう言う。
「よそう、また夢になるといけねえ」──あれは落語の名台詞です。
なぜ名台詞かというと、この噺は「夢」と「現実」が紙一重だからです。
一杯の酒で、せっかく作り直した人生がまた“夢”に戻ってしまう。
その怖さと可笑しさが、あの一言に詰まっている。
この「芝浜」について、昔、立川談志師匠がこう言ったそうです。
「この噺はな、亭主と女房が勝手にしゃべるんだ」
つまり、噺家が筋を押していくんじゃなく、登場人物が自分の意思で動き出す。
演者にも先が読めない。普通なら、そんなのは怖い。
ところが師匠は、最後にこう締めた。
「……まあ、悪い体験じゃあなかった」
自分が支配できない瞬間を、怖がるどころか“面白がる”。この一言が、実にかっこいい。
で、ここからが私の話です。
私はある日、「芝浜」をやっている最中に、
本当に“噺じゃないもの”が勝手にしゃべり始めたことがある。
客席です。スマホが♪ ピロリロリ〜ン
「来た……!談志師匠の言ってたやつだ!」
しかも止まらない。劇中の亭主も女房も、一瞬で黙った。こっちも黙った。
夢から覚めたみたいに、場内が現実に戻った。
だから私は、噺を現実に合わせて戻すしかないと思って、こう言った。
「よそう、また携帯が鳴るといけねえ」
すると、お客さんが笑った。
「芝浜」は夢と現実の噺。そこへスマホが割り込んだ。
でも名台詞があるから、現実を噺に回収できた。
しかし、「……まあ、悪い体験でした」