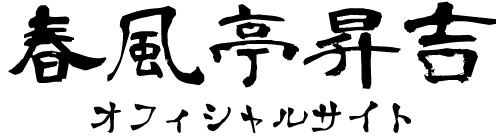48.ちりとてちん
町内に住む旦那の家では、碁会のために御馳走をたっぷり用意していた。しかし急に集まりが中止になり、料理が大量に余ってしまった。
そこへ呼ばれてやってきたのが、お向かいの褒め上手・竹さん。どんな料理でも「こいつぁ寿命が延びます」と持ち上げる男で、旦那もつい機嫌がよくなる。
一方で、同じ長屋の寅さんは真逆。人に平気で文句をつけ、礼も言わない皮肉屋。旦那は以前から腹に据えかねており、「一度ぎゃふんと言わせたい」と思っていた。
そこへ、台所から“とんでもないもの”が見つかる。数日前にしまい忘れた豆腐。青カビが浮き、鼻をつく悪臭。旦那はひらめく。
「これを珍味と称して、虎さんに食わせてみよう」
豆腐をぐちゃぐちゃに潰し、唐辛子をまぶして真っ赤に仕立てる。“正体不明のなにか”が完成した。名前がなければ怪しまれる。そこで旦那は口三味線の音から「ちりとてちん」と命名する。
呼び出された虎さんは、出された料理にいつもの調子で文句をつける。
「鯛? たいしたもんじゃねぇ」
「この酒? うまくないな」
そこで旦那が切り札を出す。
「珍味をいただいたんですよ。長崎名物の“ちりとてちん”、ご存じでしょう?」
寅さんは知ったかぶりの常習犯。知らないと言えない。
「なに言ってやがる。あっちにいた頃は、しょっちゅう食ってたよ」
運ばれてきた“ちりとてちん”。鼻を曲げる刺激臭。寅さんは一瞬ひるむが、後に引けない。
「まずは目で味わうんだよ、通はよ……く、くさっ!」
涙をこらえ、震える箸で口へ運ぶ。飲み込んだ瞬間、身体が跳ねるように震え、目から涙、鼻から汗。どう見ても悶絶しているのだが、ひきつった笑顔で言い張る。
「う、うまいねぇ……ね、涙が出るほど」
旦那は堪えながら尋ねる。「さぞ美味かったでしょう。どんな味です?」
寅さんは震える声でひと言。「……ちょうど、豆腐が腐ったような味だ」
見栄と体面が、人間をどこまで愚かにするかを描いている。
寅さんは、“知っている風を装うこと”で自尊心を支えている。しかし、その薄っぺらなプライドが、自分を最悪の苦行へと追い込んでいく。
さらに、落語の面白さは「言葉の嘘」と「身体の本音」がズレる瞬間に生まれる。
涙目で「うまい」と言う竹さんの姿は、“人間の弱さと愛嬌”そのもの。