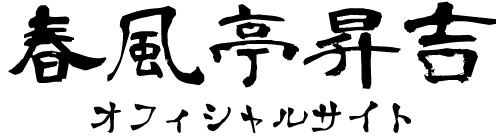東大奇人群像①「餃子男」
東大生活が始まった。田舎ではずっと、『嫌われる勇気』の先天的保持者されてきた私だが、東大ではなぜか妙に居心地がいい。理由は簡単。大学には、現代前衛芸術の作品のような才人がゴロゴロいたからだ。ちなみに、一般的な東大生のことを、学内では自嘲的に「イカ東(いかにも東大生っぽいの略)」と呼んでいた。量産型のイカ東は目を引かないが、私の人間考察のセンサーがビビッと反応する興味深い御仁がたくさんいた。
まずは、「餃子男」である。
私は、数学が苦手なのに、うっかり、食いっぱぐれにくいだろうと、経済学部に入ってしまったため、本郷での「数理統計」という拷問のような講義に泣かされていた。黒板は数式の海。∫(積分)の中に、Σ(シグマ)、e(ネイピア)、∞(無限)と、記号が溢れている。先生のチョークは止まらず、90分の授業の後にはノートが一冊まるごと消費されている。「これは数学なのか、それとも速記術の修業なのか」と、一心不乱に板書を写し続ける毎日だった。
そんな修羅場のような日、大教室の片隅にふわりとかすかなニンニクの香りがした。「なんだろう?」と周りを見回すと、カチャカチャと小さな音。ちらりと視線を送ると、中国人の留学生が、誰にも気づかれぬよう、まるで忍者のような手つきで餃子を包んでいた。教科書を立てて死角を作り、膝の上で静かに餃子を包む。左手に皮、右手に具材。芸術的な手つきで美しいひだを折る様子は、ほとんど魔法だった。まわりの「イカ東」たちは誰も気づかない。先生も板書に没頭している。彼がなにを考えているのか、私の持っている方程式では解けない。完全な未知数Xだ。
思わず小声で尋ねる。
「ノート取らなくて大丈夫なの?」
彼は、落ち着いた、流暢な日本語で答えた。
「式は教科書に書いてあるんだから、ノートには取らないよ」
私にとっては板書の写経は命綱。頭の中には何も残っていない。「無」だ。
講義が終わると、彼は餃子を綺麗に並べたトレーを手に、爽やかに立ち上がる。品の良い口調で、「これからアパート帰って、焼いて食べるんだ」と一言。ニンニクの残り香だけが私をやさしく包み込んだ。
後日、私は現実に打ちのめされる。私の数理統計の成績は「不可」。あれだけ頑張ったのに…。理解していないのに、いくら機械的に数式を書き写してもしょうがない。そんな単純なことも、当時の私にはわからなかったのだ。しかし、だからって、どうすればいいんだ。この単位がとれないと、卒業はできない。
肩を落としていた、ある日の昼下がり。学食の隅の席でぼんやりと再履修の教科書をめくっていると、見覚えのある姿が現れた。
「やあ。」
それは、例の「餃子男」だった。彼はトレイに載せた学食の定食を持ち、僕の前の空いた席に座ると、さりげなく袋からタッパーを取り出した。どうやら追加のおかずとして手作り餃子を詰めてきたらしい。
「これ、昨日の夜に包んだやつ。よかったらどう?」
そう言って彼はタッパーの蓋を静かに開けた。中にはいくつかの種類の餃子が、無造作に並んでいる。彼は特に気負う様子もなく、そのままタッパーを僕のほうに押しやった。たぶん「好きなだけ食べてくれていい」という無言の合図だ。僕は少しだけ迷ってから、餃子を二つ、それからもう一つ取った。餃子はまだ、昨日の夜の名残をわずかに抱えていて、冷たいけれど、どこかなつかしい、そういう種類の温もりをもっていた。
僕が黙って餃子を味わっていると、彼は箸を置いたまま、ふと遠くを見るような目つきになって言った。
「再履修、大変?」
言葉は軽いけれど、どこかこちらの心の奥にふれるような響きをもっていた。僕は小さくうなずき、彼の差し出した餃子をもうひとつ手に取った。
餃子の皮包みの名人は笑顔で、何ともいえない優しさに包まれていた。聞けば、彼の数理統計の成績は堂々の「優」だったらしい。
時が経ち、ふと思う。
もしあのとき、私も餃子を包んでいたら単位が取れていたのだろうか?いや、やっぱり無理だろう。
それでも、思い出すのは、あの日の教室の片隅に小さく広がった餃子の優しい香り。
そして「餃子男」がその後どうなったかは、私は知らない。謎に包まれたまま。