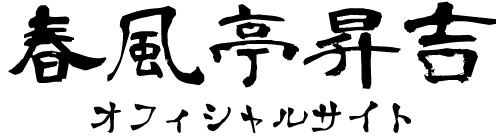「メロンと師匠と、声が消えた日」
前座の後半、3年目、4年目、毎月四十本ぐらいの仕事をこなすようになっていたころ、僕はすっかり疲れ果てていた。自ら望んだことだとはいえ、体がついていかない。
体調管理はプロとして当然だという点は重々承知していたが、現実は「気合いと根性」で乗り切る昭和スタイル。結果、「令和の過労死予備軍」と化していた。
そんな中、落語芸術協会の北海道一週間落語ツアーに選ばれた。
夕張といえば『幸福の黄色いハンカチ』の舞台。みんなで映画のロケ地に行き、「ああ、これが高倉健の立ってた場所かぁ」と感慨にふける……かと思いきや、僕はそれどころじゃなかった。なぜなら、僕にはこの旅最大の敵がいた――夕張メロンである。
メロンアレルギーの僕にとって、夕張はほとんど「メロン界のラスボスが待つ最終ステージ」。行く先々で「ほれ、名物だ」と夕張メロンを勧められ、「すみません、アレルギーでして」と断るたびに、まるで異星人を見るような目で見られる。
メロンジュース?アウト。
メロンアイス?即死。
メロンパン?メロン成分が入っていなくても、名前だけで警戒態勢に入ってしまう。
師匠たちは、「こんなにおいしいのを食べられないなんて、かわいそうだねぇ」と言いながら、口の中でとろけるメロンに恍惚の表情。こっちは香りを嗅ぐだけで喉がかゆくなり、脳内でアレルゲンアラートがフル稼働。
そんな中、みんなでお土産を買いに「夕張メロンドーム」なる場所へ。屋根に巨大なメロン型ドームが載っていて、「ああ」と、メロンの総本山に苦笑い。
店に一歩足を踏み入れると、そこはゼリー、ケーキ、ソフトクリーム、チョコレート、メロン酒、ついにはメロンコスメから、メロン石鹸まで。もう「飲む・食べる・塗る・洗う」全方位メロン攻撃。
その濃厚すぎる香りに、僕の喉は一発ノックアウト。咳き込むどころか、「誰か人工呼吸器を!」と叫びたくなるほど。慌てて店の外に出たものの、喉の痛みはおさまらない。
師匠と先輩たちが出てきて、「どうした昇吉、大丈夫か?」
「大丈夫です……」と答えたその声は、限界だった。
水を飲み、うがいをし、のど飴をなめ、最終的には「南無阿弥陀仏」とお経まで唱えたが、声は一向に戻らず。このままじゃ夜の高座は無声落語になってしまう。落語なのにサイレント映画。ちょっとオシャレかも。
半泣きになりながら師匠に電話すると、「お前、何やってんだよ!」と怒鳴られるかと思いきや、意外にも驚くほど優しい声で、「今すぐ病院行きなさい」と。
このギャップに、不覚にも少しキュンとした――と言いたいところだが、それ以上に胸が熱くなったのは、その声の向こうに、心底こちらを心配してくれる気持ちがにじみ出ていたからだ。
その後も、しばらくして師匠からもう一度電話がかかってきた。
「薬はちゃんともらったか?ちゃんと診てもらったんだろうな?」
普段なら「自己責任でやれよ」と突き放しても不思議はない人なのに、このときばかりは、まるで親が子を心配するような口ぶりだった。
さらに東京に戻ってからも、「まだ治らないなら、俺の行きつけの病院に行きなさい」と、自ら病院を紹介してくださった。その病院は、舞台人やアナウンサーなど“声を商売道具にする者”が多く通う、いわば「喉の駆け込み寺」だった。
普段は「まあ、お前も適当にやりな」と笑っている師匠なのに、いざというときには驚くほど細やかで、実に的確に手を差し伸べてくれる。
「本当の優しさは、必要なときにだけ、さりげなく現れる」――この人こそ、それを地で行く人なのだ。
結局、四日間も寄席を休む羽目に。その間ずっと「もう二度と限界まで働くのはやめよう」「あのメロンドームに入ったのが運の尽きだった」と反省しきり。
……そう心に誓ったはずなのだが――。
その後、二つ目になり、これ以上に忙しくなった。ほとんど寝ておらず、連日働きづめ。
貧乏性で仕事が断れないし、やりたいことが多すぎる。最近は「休みたい」が口癖だが、いざ休みができると、「せっかくだからなんかやろう」と予定を詰めてしまう。
人間、学習よりも習性のほうが、ずっと手ごわいらしい。
※ちなみにこの原稿も、午前三時に書き終わった。そして、あのとき紹介してもらった病院の電話番号は、今も携帯に“緊急用”としてしっかり登録してある。